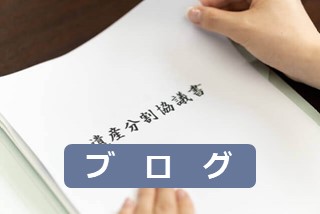事務所概要・お問合せ・報酬額など
扶養義務とは
扶養義務とは、扶養義務者(扶養してあげる人)が、自分の所得のみでは自立した生活を送れない扶養権利者(扶養を受ける人)を経済的に援助する義務を負うことです。
扶養権利者は、扶養義務者に対して経済的援助を求めることができます。扶養義務は、生活保持義務、生活扶助義務というふたつから成り立っています。
- 生活保持義務
扶養義務者自身と同水準の生活を被扶養者にも保障する義務です。これは、共同生活の必然性から生じるものなので、被扶養者の配偶者、未成熟子である被扶養者の両親が義務を負います - 生活扶助義務
生活基盤(単位)が異なる親族が、扶養義務者自身の生活水準を確保していることを前提として、余力の範囲で被扶養者の最小限の生活を保障する義務です。兄弟姉妹や、成人した子に対する両親の扶養義務です
親族間の扶養義務の範囲
「親戚にはお互いに扶養し合う義務があるから面倒を見なければならない」などとおっしゃる方がおられますが、扶養義務には範囲が定められています。
民法877条では扶養義務者を以下のように定めています。
- 直系血族および兄弟姉妹
直系血族は血の繋がりがある自然血族と養子等の法定血族です。兄弟姉妹が結婚して戸籍から除かれた場合であっても、被扶養者との間で法律上は兄弟姉妹なので義務は残ります - 特別の事情があるときの3親等内の親族
扶養義務を負う直系血族と兄弟姉妹、配偶者に経済力が無い特別な場合で、家庭裁判所が審判によって扶養義務者とすることができます - 配偶者
民法752条では、夫婦は同居して相互に扶助しなければならないと定めています。離婚の場合に該当することが多い扶養義務です。離婚相談も当事務所にお任せください
親族間の扶養義務の内容
扶養義務の具体的な内容については民法でも定められておらず、原則は協議で定めることになります。協議で定まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で定めることになります。
扶養義務者の順位
扶養義務者が複数いる場合、扶養義務を負う順位をつけます。扶養義務者間で協議して決めることが原則ですが、協議で定まらない場合は家庭裁判所によって扶養の順位が定められます。
なお、相続や遺言書作成の場合には、最も基本的である相続人の順位について考慮する必要があります。扶養義務の順位とは異なり、相続人の順位は法で定められています。
民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割の手続き
- 相続土地国庫帰属制度
行政書士かわせ事務所の公式HP「相続手続き」ページはこちらから
事務所概要・お問合せ・報酬額など