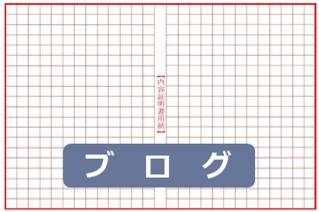事務所概要・お問合せ・報酬額など
内容証明の書式
まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。
紙ベースの内容証明は1枚あたり26行以内で1行あたり20文字以内というルールがあります。タテ、ヨコは不問ですが内容証明の専用紙は縦書きで販売されています。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、細かいですが料金も割増しになります。
一方の電子内容証明は、最大で5枚までとされていますが、1枚あたりは1,584文字までOKなのでこちらの方が作成しやすいと思います。電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。
当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります
内容証明の文面記載例
記載例(タイトル)
実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。
とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。
記載例(宛名等)
ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合、男性は「貴殿」とし、女性は「貴女」とするのが一般的です。内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。
不貞行為の慰謝料請求などの場合は、相手方が女性でもあえて「貴殿」とすることもあります。ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。
記載例(冒頭)
通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。
行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。
記載例(内容)
ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。
記載例(最後の宛名部分)
最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名と併せて代表者氏名も記載します。
なお、紙ベースの内容証明の場合は作成した用紙を封筒に入れなければならず、この封筒にも通知人と被通知人の住所と氏名を記載することになります。用紙に記載した住所と氏名は封筒に記載するときも全く同じにする必要がありますのでご注意願います。
DVをやめることを要求する内容証明
DVで内容証明を差し出す状況とは
DVはいろんなシーンで発生することが想定されます。DVとはドメスティック・バイオレンスなので、夫婦間での暴力が一般的です。当記事は夫婦間でのDVを想定して記述しています。
もしDVを事由として離婚になる場合は当記事のようなDVをやめてもらう旨の要求ではなく、離婚(協議離婚)へ向けての動きになります。離婚に合意した時点で離婚協議書を作成し、その中に離婚事由や慰謝料についての条項を記載することになります。
また、DVが発覚したものの離婚するのではなく、言動等を改めてもらい夫婦生活を継続するのであれば、DVに関する合意書を作成することになります。夫婦間で話し合い、もうDVは二度としないという旨の合意書です。
当記事は内容証明という証拠能力が高い方法でDVをやめてもらう旨の意思表示をするケースです。内容証明は「喧嘩を売っている」と受け取られることも多く、覚悟を持って発送しなければなりません。
想定されるのはDVにより別居を始めるケースです。直接、配偶者に対してDVをやめて欲しいと言えない(畏怖等により)状況であったり、やめて欲しいと言ったところで話し合いにならない状況です。
DVをやめる要求の記載
内容証明の作成は、まず婚姻日を記載し、同居義務を履行しつつ夫婦生活を共にしていたことから書き始めます。そして、DVが始まったのはいつ頃からか、何度ぐらい、どんな暴力かを追って記載します。
DVが始まった当初、こんな風になるとは思ってもいなかったと思いますので、回数まではわからないことがほとんどでしょう。その場合は「再三にわたり」や「何度も繰り返し」などの文言で構いません。反対に、日記やメモに残している方は詳細に記述できると思います。
内容証明を差し出そうとしたきっかけとなった暴力が最後にくると思います。ここは年月日をはっきりと記載し、暴力の態様も詳しく記載します。暴力を受けたときに診療を受けたり診断書をもらっている場合は全治期間と傷病名も記載します。
次に、本題となる今後一切暴力を振るわないことを要求します。そもそも暴力行為は刑法の傷害罪なので刑事告訴をすることも可能です。「今回は見逃すが次は無いぞ」という内容で記載してもいいと思います。より深く反省させる手段としては有効です。
裁判所や警察に助けを求める方法もある
身の危険を感じる場合には、迷わず警察に相談することをおすすめします。よく「警察は民事不介入だから何もしてくれない」と耳にしますが、刑法上の罪なら話は別です。
警察を頼り、傷害罪や暴行罪で告訴をするという方法もあります。告訴状を受理した警察は必ず捜査をしなければならないのですから。話し合いすらできない相手であれば裁判所や警察(検察)に助けを求めて戦うことも視野に入れておかなければなりません。
なお、ご自身はつらい思いをしたりケガをしたりしているので、どんな状況でどんな真実なのかわかっているのですが、裁判所や警察といった機関では主張を裏付ける資料や証拠が必要な場合が少なくありません。
「いずれ役に立つかも、いずれ決め手になるかも」将来的なことはどうなるかわかりませんが、出来る限りの資料や証拠を準備することを推奨します。過去に遡って証拠を作ることはできないのですから。
郵便法
第四十七条(配達証明) 配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第四十八条(内容証明) 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
事務所概要・お問合せ・報酬額など