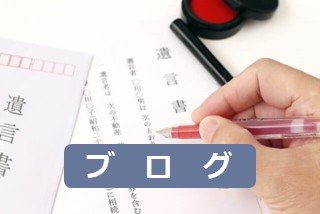事務所概要・お問合せ・報酬額など
検認の手続きとは
検認の手続きとは、家庭裁判所で相続人の前で、発見された自筆証書遺言を開封して確認する手続きです。通常、自筆証書遺言は封をしてあります。
しかし、相続人が勝手に開封してはいけません。勝手に開封すると、5万円以下の過料の処分をうける場合があります。検認の手続きは、遺言書に書かれた内容の法的効力などを確認するものではありません。
検認は遺言書の内容が有効なのか、無効なのかを家庭裁判所で判断してもらう手続きではなく、遺言書の偽造・変造等を防ぐために、遺言書が発見された事実を相続人の間で共有する手続きです。
しかしながら検認の手続きをしていない遺言書(自筆証書遺言)は相続手続き(遺産分割の手続き)に使用することはできませんので必ず検認手続きをする必要があります。
検認手続きの流れ
(1)検認の申し立て
遺言書を発見した相続人が申立人となり、家庭裁判所に検認の申立てをします
(2)検認の通知
家庭裁判所から申立人、すべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます
(3)遺言書の開封
検認の期日に、申立人および相続人立会いのもとで、遺言書が開封されます
(4)遺言書の内容確認
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等遺言の内容がどうなっていたのかを確認します
(5)検認調書の作成
遺言書の内容確認の結果を、家庭裁判所が検認調書にまとめます
(6)検認済証明書の発行を申請
相続人は家庭裁判所に検認済証明書の発行を申請する
検認の手続きは、家庭裁判所に申立てをしてから1か月ほどかかりますので早めにしなければなりません
早めにしなければならない理由は、相続手続きには期限が設けられているものがあるからです。相続の方式を決める熟慮期間は3か月以内、相続税申告が必要な場合は10か月以内と定められています。
家庭裁判所で発行される検認済証明書は自筆証書遺言と併せて初めて遺言書となり、遺産分割の手続きに添付できるようになるとお考えいただくとわかりやすいかと思います。
検認の手続きが不要となる遺言書がある
以上のように、検認の手続きは相続人が全員集合しなければならず、手続きの期間もかかります。しかし、この検認の手続きが不要となる遺言書も作成できます。
まずは、公正証書遺言です。公証役場で作成する遺言書であり、この方式で作成すると検認は不要となります。なお、公証役場では遺言書作成についての解説、指導、アドバイスをするところではありません。
遺言書は相続手続きのための法的効力を持つ書面ですので、遺言書案の作成は専門家に依頼することを推奨します。なお、公正証書遺言の作成は公証役場への手数料と作成期日に立ち会う証人2名への報酬支払いが必要です。
もうひとつは、自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。先述したように通常の自筆証書遺言では検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度の制度を利用すると検認は不要になります。
しかも作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえますのでおすすめです。公正証書遺言の場合は、一度作成した公正証書遺言を書き直したい場合にとても大変です。
自筆証書遺言なら簡単に書き直せるのでこの方法がおすすめです。自筆証書遺言書保管制度は管轄の法務局で受け付けしています。
この制度は新しい制度なので専門家に依頼する際には、自筆証書遺言書保管制度(さらに自筆証書遺言の緩和策にも)に対応しているか確認してからの方がいいと思います。
遺言書は遺書やエンディングノートとは異なり、法的効力を持つ書面ですので、いざ相続の開始のときに遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
反対に遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をしなければならないので相続人の負担は一気に増加してしまいます。
自筆証書遺言書保管制度を利用してできること
- 遺言書を預ける(遺言書の保管の申請)※遺言者がする
- 預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)※遺言者がする
- 遺言書を返してもらう(撤回)※遺言者がする
- 変更事項を届け出る(変更の届出)※遺言者がする
- 遺言書が保管されているか確認する(遺言書保管事実証明書の請求)※相続人がする
- 遺言書を見る(遺言書の閲覧)※相続人がする
- 遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の請求)※相続人がする
民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
事務所概要・お問合せ・報酬額など