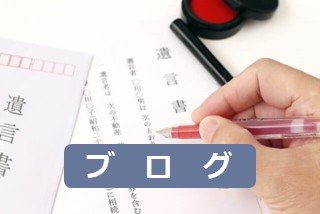事務所概要・お問合せ・報酬額など
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる新しい制度です。今まで自筆証書遺言書を作成した場合は自分で場所を決めて保管しなければなりませんでした。
お仏壇や金庫などに保管することが多いのですが、偽造・変造などの危険が伴います。法務局で預かってもらえると、このようなリスクを回避できます。
さらに自筆証書遺言書保管制度にはもうひとつ大きなメリットがあります。自筆証書遺言書は遺言者の亡きあと、遺言書を発見した相続人はその場で開封せずに、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認は相続人が集まり、皆の前で開封する手続きです。自筆証書遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言書を作成すると検認が不要となり、すぐに相続手続きをすることができるのです。
遺言書の方式
遺言書の方式について記述します。遺言書には下記の3種類の方式が定められています。それぞれの法定の方式に沿った方法で作成することが重要です。ちなみにエンディングノートは法的効果はありませんので相続手続きには使えません。
- 自筆証書遺言
すべて自分で書く遺言書です。代筆、連名、パソコン作成は不可です。公正証書遺言のような手数料がかからず手軽に作成できます。遺言書を発見したら検認の手続きが必要です。 - 公正証書遺言
公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書です。公証役場では作成の指導やアドバイス、検討はしてもらえません。まずは専門家に依頼し、遺言書案を作成することが最も重要です。なお、公証役場への手数料と証人2名への報酬支払いが必要です。 - 秘密証書遺言
ほとんど利用されていない方式なので割愛します
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言書保管制度は自筆証書遺言のデメリットをなくすことができる画期的な制度だといえますので当事務所でも推奨しています。
公正証書遺言の場合と同様に、法務局(遺言書保管所)では遺言書の作成方法の指導や、内容についてのアドバイスなどは一切してもらえませんので、まずは遺言書(案)を作成する必要があります
保管の申請の際も内容については触れることもなく、あくまでも「保管」してくれるだけです。また、自筆証書遺言書保管制度の代理申請は認められておらず、ご自身でしなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、自筆証書遺言書保管制度に対応している専門家に依頼して、まずは遺言書を作成する必要があるのです。
自筆証書遺言書保管制度で利用できること
自筆証書遺言書保管制度によって出来るようになった様々な手続きを簡潔にご紹介していきます。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は予約制となっています。
自筆証書遺言書保管制度で出来る手続きは、遺言者本人がする手続きと、遺言者の死亡後に相続人等がする手続きに区別されています。
(1)遺言者が遺言書を預ける
遺言書を保管してもらう手続きです。保管の申請が出来るのは遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。長浜市と米原市の管轄は長浜法務局です。
(2)遺言者が預けた遺言書を見る
遺言者は、預けた遺言書を閲覧をすることができます。閲覧の方法は、モニターで画像確認または遺言書原本の閲覧です。
モニター閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能、遺言書原本の閲覧は保管されている遺言書保管所のみ可能です。
(3)遺言者が預けた遺言書を返してもらう
遺言者は、遺言書保管所に預けた遺言書を返してもらうこともできます。これは保管の申請の撤回といいますが、手続きは遺言書原本が保管されている遺言書保管所のみで出来ます。
遺言書の内容を書き換えたい場合は、撤回をして返してもらい、また新たに保管の申請をします。手数料は不要。
(4)遺言者が変更事項を届出する
遺言者は、保管の申請時以降に氏名・住所等が変更になったときは、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。
変更の届出は遺言者ご本人とその親権者や成年後見人等の法定代理人がすることができます。手数料は不要。
(5)相続人等が遺言書が保管されているか確認
相続人等が、遺言者が亡くなったあとで、遺言書が遺言書保管所に預けられているかを確認する手続きです。全国のどの遺言書保管所でも交付請求することができ、送付の方法も可能です。
(6)相続人等が遺言書を見る
相続人等は、遺言者が亡くなったあとで、遺言書の閲覧の請求をして遺言書保管所に預けられている遺言書の内容を閲覧することが出来ます。閲覧の方法は、モニター画像閲覧または遺言書原本の閲覧となります。
モニター閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能で、遺言書原本の閲覧は保管されている遺言書保管所のみ可能です。
(7)相続人等が遺言書情報を取得
相続人等は、遺言者が亡くなったあとで「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができます。遺言書情報証明書は、まさに遺言書を写したようなイメージのものです。全国のどの遺言書保管所でも請求できます。
送付の方法による請求は、自分の住所を記載した返信用封筒と切手を同封しましょう。遺言書情報証明書は、登記や各種相続手続きに利用でき、家庭裁判所の検認の手続きは不要です。
また、相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官は請求人以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します
自筆証書遺言の緩和策
自筆証書遺言書保管制度のほかに、自筆証書遺言の方式緩和の法改正が2019年1月13日に施行されています。先述したように、自筆証書遺言はその全てを自書で作成しなければなりませんでした。
本改正により、財産目録をパソコンで作成、通帳のコピー、不動産登記簿謄本を添付することが認められるようになりました。
これらのすべてに、本文に押印した印鑑で署名押印すればよいことになります。これにより、自書しなければならない部分が大幅に少なくできます。
遺産自体は変更しないが、分割する相手や割合を変更したい場合も、本文だけの書き換えで済むため大きなメリットです。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
事務所概要・お問合せ・報酬額など