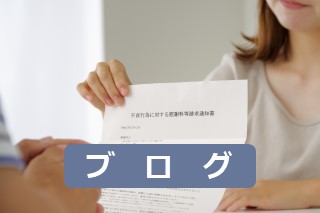事務所概要・お問合せ・報酬額など
養育費の取り決めは必須
養育費とは、離婚後に子の非監護者から監護者へ支払われる子の養育・監護に関する費用です。子がいる夫婦が離婚をするときには、必ず取り決めをしなければなりません。
通常、離婚をするときには養育費以外にも財産分与など取り決めをするものがあります。夫婦間でこれらの取り決めをして、これらを証するものとして離婚協議書を作成します。
離婚協議書は、離婚届を提出する前に作成します。このように、離婚協議書を作成することがマストですが、「一日でも早く離婚したい」など、様々な事情によって離婚協議書を作成せずに離婚届を提出してしまうこともあります。
よって、養育費についても取り決めをせず、または口約束で「毎月●万円」と決めてしまうことも少なくありません。当記事は、養育費の取り決めをせずに離婚してしまった場合、養育費の増額・減額をする場合、養育費の支払終期を延長する場合について解説します。
養育費の取り決めをしていなかった場合
養育費の取り決めをせずに離婚をしてしまい、離婚後に養育費の取り決めをする場合は、当事者同士で協議をし、整った場合は「養育費についての合意書」を作成します。
養育費についての合意書は、離婚協議書を作成する場合の「養育費」の条項を抜き出したようなものです。毎月の支払額だけではなく、支払いの始期と終期、支払期日、支払方法なども詳細に取り決めます。なお、養育費の金額については別記事をご覧ください。
当事者間で協議しても合意できない場合は、家庭裁判所に申立てをして調停をすることになります。養育費は非常に強い権利なので支払いを免れようとすることは避けた方が賢明です。例え自己破産をしても養育費の支払いは免責されず、給与の差押え(強制執行)の場合は2分の1まで押さえられます。
養育費を請求しない旨の取り決めをしていた場合
離婚を早く決めたい場合など、養育費の請求は今後もしないと約束する場合もあります。当事務所で離婚協議書を作成する場合には、このような条項は記載しません。
養育費を請求しない旨の約束は、父母間では有効ですが、子が親から扶養を受ける権利としては放棄や無効にはできないからです。協議で合意できない場合は家庭裁判所に申し立てをします。
養育費は、子の扶養請求権に依拠しているので、父母間の養育費不請求の合意は無効の判例もあり、子が有する扶養請求権には影響を及ぼしません。
なお、令和6年の養育費についての法改正では法定養育費が創設され、養育費の確保についても見直しがされます。(令和8年4月1日施行)
取り決めていた養育費の額を変更する場合
離婚の際にきちんと養育費の取り決めをしていたものの、その金額を増額したい場合や、反対に減額したい場合です。当事者間の協議が整えば「養育費増額(減額)の合意書」を作成します。
取り決めをした養育費の金額は、何があっても変更できないというわけではありません。当事者間で協議が整わない場合には家庭裁判所に申立てをし、調停にて取り決めをすることになります。
家庭裁判所では、養育事情に後発的変更があったと認められるか否か、ここを重視して調停を進めていきます。養育費増額請求の調停で考慮される事情は以下のとおりです。
- 入学、進学による費用
- 病気や怪我による治療費
- 受け取る側の転職や失業による収入の低下
- 物価水準の大幅な上昇
養育費の取り決めをした(離婚時点)時点では予見することができなかった、後発的な事情変更といえるかどうかがポイントです。反対に養育費減額請求の調停で考慮される事情は以下のとおりです。
- 支払う側の病気
- 支払う側の転職や失業による収入の低下
- 受け取る側の収入の増加
再婚した場合の養育費
まずは、離婚後に権利者(養育費を受け取る人)が再婚した場合を考えてみます。養子縁組した場合は、権利者の配偶者が養親となります。扶養義務については、養親が第一次的な扶養義務者となり、義務者(養育費を支払う人)は養育費の支払いを免れたり、減額されたりする可能性があります。
養子縁組していない場合については、減額は認められにくくなります。養子縁組があっても、義務者の扶養義務がなくなるものではありませんが、権利者の再婚相手は権利者に対して扶養義務を負うため、経済的余裕が生じ、養育費が減額になる可能性もあります。
一方、義務者が再婚して再婚相手に収入が無い場合や、新たに子が生まれた場合は減額が認められやすくなります。再婚相手に十分な収入があったり、子がない場合は扶養の必要がないので難しいといえます。
養育費の支払終期の変更をする場合
養育費の取り決めのなかで、支払終期についても定めていると思います。現在、成人年齢は18歳ですが、養育費の実務上は20歳を基準とすることが多いです。
法定養育費が創設されますが、その中では18歳とされますので、今後は18歳までが多くなるかもしれません。いずれにせよ、協議離婚で養育費の取り決めをするのであれば、18歳でも20歳でも大学卒業でも、当事者が合意できればよいことになります。
支払終期を取り決めたものの、終期を延長したい場合は「養育費の終期延長についての合意書」を作成します。
参考:支払始期について
養育費の支払始期についても記述しておきます。養育費は、請求の意思表示をしたときが始期となります。調停・審判で決する場合は、申立て時が支払始期です。
調停・審判の申立てをする前に、内容証明で請求しておくと、この日が始期となる場合もありますので、少しでも早く請求することが重要と言えます。
なお、事前には請求しておらず、調停・審判で請求した場合には、過去の分の支払いは認められず、申立て時以降の分が認められることになります。
当事務所では男女問題の書類作成はもちろん、離婚協議書の作成も承ります。離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。
まとめ
- 離婚の際に養育費の取り決めをして離婚協議書にしておくことが基本
- 養育費の取り決めをせずに離婚をしてしまった場合、当事者同士で協議をして整った場合は「養育費についての合意書」を作成する
- 令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により、法定養育費が創設され、養育費の確保についても見直しがされる
- 養育費の取り決めをしていたものの、金額や支払期間を変更する場合でも合意書を作成する
民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
- 男女関係解消の合意書作成
- 内縁関係解消の合意書作成
- 婚約解消の合意書作成
- 別居に関する合意書作成
- 婚姻費用分担の合意書作成
- 不貞行為の示談書作成・不貞行為の誓約書作成
- 養育費に関する合意書作成 など
行政書士かわせ事務所の公式HP「男女問題」ページはこちらから
事務所概要・お問合せ・報酬額など